
5歳児クラスで部分実習があるけど何やればいいの~!!
何も思いつかないよ…
部分実習で何をやればいいのか分からない・決まらないという実習生さんもいるかと思います。
今回は私が実習生だった時に実際にやった部分実習の内容をご紹介していきます。
とても簡単な内容になっているので是非参考にしてみてくださいね。
この記事はこんな方におすすめ
- 5歳児の部分実習で何をやろうか悩んでいる
- 部分実習での流れが思いつかない
- 部分実習での注意点や用意・考えておくべきことを知りたい
部分実習で何をやるか決めている人も反省点や考察は参考になると思いますので是非目を通してみてください♪
部分実習クラスの詳細
- 年齢:5歳児クラス
- 時間:30分間
- クラスの特徴:割と落ち着いている
保育園5歳児の部分実習で実際に私がやったこと・流れ
私は部分実習でカエルのマラカスづくり」をしました♪

ちょっと再現するために即席で作ったのでだいぶ雑ですがこんな感じのものです。
実際には画用紙のサイズはペットボトルに入るぎりぎりの長さにし、もう少し絵が大きくわかりやすく作っていました。
ビーズがなかったので代わりにピンクのポンポンを入れています(;'∀')
準備するもの
- 500㎖のペットボトル
- ビーズ
- クレヨン
- 画用紙
制作の内容自体は写真でイメージが沸くくらいにとても簡単なものです。w
ただ、慣れない部分実習に余裕を持って取り組みたかったのでやってみてちょうどいい内容だったかなと思っています。
作り方
下準備
あらかじめペットボトルに入るサイズに画用紙をカットしておく
- 画用紙にクレヨンでカエルの絵を描く
- ペットボトルの中に入れる
- ビーズもペットボトルに入れる
- 蓋を占めて完成
私はやらなかったのですが、ふたを閉めた後にビニールテープで止める工程もプラスすれば、ビーズなどが散らばる心配がありません。
手遊びで導入
「はじまるよ」という手遊びで導入をしてクラス全体の気をこちら側に向くようにしていきました。
園児たちも「これから何が始まるんだろう?」と期待を持てるようこの手遊びにしました。
作り方の説明をする
最初にあらかじめ作っておいた完成品を見せ、「今からこれを作っていくよ」という風にこどもたちに完成のイメージが浮かぶようにしていきます。
この説明の段階で予想できる注意点も子どもに伝えておき、部分実習中のトラブルをなるべく防ぐようにしていきました。
注意事項の説明例
- クレヨンの数には限りがあるため友達と譲り合うこと
- ビーズはこぼしやすいので実際に使う時まではしまっておくこと
こどもたちが制作に取り掛かる
制作に取り掛かりだす子どもたちを見回りながら、実際に自分が計画した部分実習の内容に取り組む子どもたちの姿を見て意外だった点や想像通りだった点なども意識してみておくと後から先生方と反省をするときに使えます。
園児全員が作れたらみんなで「カエルの歌」を歌って終わる
時計を見ながらクラス全体を見回り、みんなが作り終えたタイミングで「制作の時間はここまで」ということを伝え、みんなでカエルの歌を歌って終わりました。
個人的な感想としては、担当の先生や、園長先生たちに見られながら、カエルの歌を演奏無しで歌うのは若干恥ずかしかったです。w
もちろん割り切ってやり切りましたが!
保育園5歳児の部分実習での注意点・反省点

ここまでやってみると色々な反省点が見つかりました。
緊張によるド忘れ
実は担当の先生と打ち合わせをする段階から決めていた部分実習導入の手遊び。
緊張で度忘れしてしまい、手遊び無しで始まってしまいました。
部分実習後の反省会でも、担当の先生や園長先生から指摘されるまで手遊びを忘れていたことさえ忘れていました。w
「導入の手遊びをやっていたらもっと部分実習のはじまりがスムーズにいったんじゃないかな」と思う面もありましたが、その緊張も今思えば大きな失敗ではなく、いい経験になったと思えています。
クラス全体がざわめく
作り方の説明をしている時など、こちら側がクラス全体に話しかけている場合にクラスがざわめきだし、説明できない時がありました。
そんな時、私は園児に対して注意が多くなってしまい、後の反省会で「注意ばかりではなく、今から楽しいことをするという期待できるような声掛けができるともっとよかったと思うよ」というご指摘をいただきました。
そして部分実習の中で静かにしてほしいあまりに「シー」とジェスチャーを交えて何度もやっていました。
私の実習園では園児に静かにしてほしい時に「シー」というジェスチャーはあまりやらない方針だったようで、確かにもう少し声掛けの仕方に工夫ができたらよかったと反省しました。
泣く子ども
- うまく書けない
- やり直したい
- クレヨンで使いたい色がない
と泣き出すこどもが出てきました。
めちゃくちゃテンパり、正直イラ立ったりもしました。
実習生だった時の私は実習時間に迫られていたので「とりあえず今ある色で早めに塗ってみて」と急かしてしまいました。
今思うと最悪な実習生ですね(;'∀')
しかし実際に保育士になってから当児を振り返ってみると以下のように対応すればよかったかな、と反省しています。
対応
- 思うように出来ない園児の気持ちを汲み取った言葉掛けをする
例:「うまく書けなくて泣けちゃったんだね。でも先生はとてもすてきだと思うよ」 - 他のみんなが注目しないように新しい紙を渡す
- 「こんな色はどう?」と提案をしてみる
「うまく書けないから」と言って画用紙を次々と渡してしまってはキリがないと思う場合は、最初の作り方の説明の段階で伝えておくことが大切です。
しかし実習中は想定外のトラブルは付きものなので、多めに画用紙を準備しておくことをおすすめします。
指示に従わない子ども
私の実習園での担当クラスではなかなか実習生(私)に心を開かない園児さんがいました。
声掛けなどしても全然従わず、担任の先生が来てからやっと動き出すという子でした。
いいのか悪いのか、部分実習の日にその子はお休みだったのですが、もしそういった子がクラスにいる場合はその子への対応を考えておくことをおすすめします。
対応の例
画用紙に絵を描かない→一緒に書くことを提案してみる
隣の子の邪魔をする→常に気にかけすぐ声掛け出来るようにする
こういった気になる子・指示に従わない子の当日の動きやどう対応するかなどはきちんと想定しておくことがポイントです。
これは実際に保育士や幼稚園教諭も何か行事ごとがある際など具体的に想定し、トラブルが起きないようにしているので必ず考えておくようにしましょう。
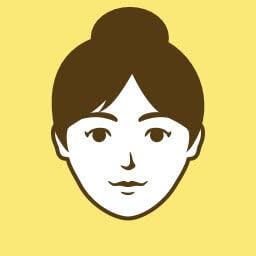
「指示に従わせる」という表現は保育士・幼稚園教諭として好ましくないので「声掛けをし促す」などと言い換えてくださいね。実習記録を書く際にも気を付けましょう。
保育園5歳児に部分実習でやってよかったこと考察

次のうちあげているものは実際に取り組んできてよかったと思っているものです。
実習では失敗したとしてもそれも学びになりますが、やってよかったことも学びとなりますので是非役立ててみてくださいね。
部分実習一週間前から手遊びの練習
担任の先生にお願いして、部分実習の導入として最初にやる手遊びを部分実習の1週間前から毎日帰りの時間に園児とやっていました。
毎日やっていく中で園児も覚えていき、部分実習の導入に備えました。
「はじまるよ」という手遊びだったので、手遊びだけで終わると違和感があったので、そのあとに一冊えほんも読んでいました。
「いるもの」を予備で準備
どのくらいの人数の子どもがやり直したがるか分からなかったので、多めに画用紙を切っておきました。
また、ペットボトルは各園児の保護者にあらかじめお願いしていたので、みんな持参してくれていましたが、万が一のトラブルに備えて何本か予備を持っていきました。
他にも実習園の教材庫からお借りしてクレヨンも多めに準備しておくなど、使う材料の中で多めに準備できるものは全て準備しておきました。
実際に予備の中から使用したものは画用紙一枚程度で他にはほぼなかったですが、用意しておくことで気持ちにも余裕が出来、ためになりました。
まとめ

部分実習というのは実習中の中でも特に先生方の注目が集まり緊張する項目のひとつですよね。
- 何をするのか
- どんなハプニングが想定できるか
- 準備しておくべきものは何か
- やっておくべきことは何か
- 練習しておくべきことは何か
この辺りをしっかり考えておき、準備しておくことがとても大切になってきます。
それに加えて
- 材料を落ち着いて何度も確認
- 材料はそれぞれどこにしまっているかの確認
- 紙に書いてみる実習のシミュレーションをしてみる
ということも併せてやっておくことで実習当日テンパるリスクはグッと下がるかと思います。
緊張からくる失敗は焦らなくても大丈夫。
どの実習生もどの保育士も経験していることです。
ただ、準備不足により先生方が残念に思わないようにしましょう。
実習生活はただでさえ、園でも帰宅後の実習記録簿でも大変だと思いますが、しっかり向き合うことで必ず将来のあなたの肥やしになります。
頑張って乗り越えてくださいね!
